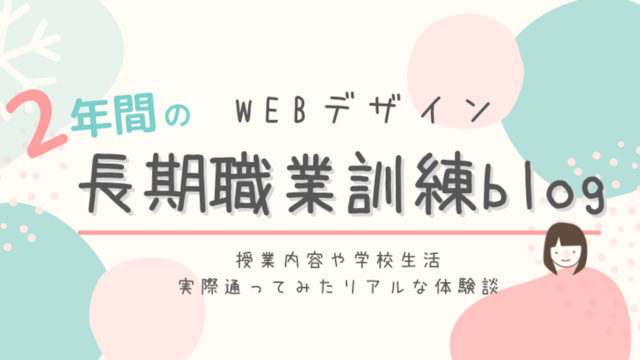薔薇の町、広島県福山市に行きました。大学時代の友人たち6人が集結、このメンバーが揃ったのは約30年ぶりのことです。福山駅前天満屋8階の又来軒で、目の前に福山城を見ながら、中華料理に舌鼓を打ち、おしゃべりはとどまるところを知りません。
駅前から送迎バスに乗り、鞆の浦へ。宿に着いたのが15時過ぎ。部屋からの眺望は抜群です。


今日は夏至、外は明るく、おしゃべりは止まらず、うっかり夕食時間に遅れてしまいました。18時半でもこの明るさ、美しさ。

屋上露天風呂を楽しみ、またまたおしゃべりは止まらず、2時まで。
夕食も朝食もとても美味しくいただきました。9時半に、鞆の浦しおまちガイドさんと約束、11時半まで鞆の浦そぞろ歩きです。
幕末「日本外史」を著した頼山陽が名付けた、「対仙酔楼」です。今でも人が住んでおられます。


仙酔島との渡し船乗り場(平成いろは丸が出港します)。
1867年5月26日(慶應3年4月23日)に鞆沖合で、坂本龍馬ら海援隊員の乗り込んだ「いろは丸」と、紀州藩所有の「明光丸」が衝突しました。
その後、紀州藩を相手に、坂本龍馬をはじめ、海援隊総掛りで賠償の交渉にあたりました。
お互いに航海日誌を提出し、衝突の原因と、責任について激しい攻防戦が行われました。その後、交渉に土佐藩の後藤象二郎が加わり、事は土佐藩と紀州藩の事件に発展、紀州藩は賠償金を支払うこととなりました。

船着場の向かいには歌碑があります。

吾妹子が見し鞆の浦のむろの木は常世にあれど見し人ぞなき
わぎもこが みしとものうらの むろのきは とこよにあれど みしひとぞなき (巻三446)
太宰府に赴任した旅の途中私の妻が見た、ここ鞆の浦のむろの木は、都への帰り道の今まで長い命を保っているのに、愛しい妻はもういない。
天平2年(730年)、大伴旅人(66歳)が九州太宰府での任期を終え、都へ帰る途中の12月、鞆の浦へ立ち寄った時の歌です。太宰府で亡くなった最愛の妻、大伴郎女をしのぶ気持ちを歌にのせています。太宰府に向かう時に、二人は神木のむろの木に航海の安全を祈りました。しかし帰り道、最愛の妻はいません。
歌碑の横に植えられているのがむろの木です。当時の神木はもっと大きな木だったと考えられるそうです。旅人は、都へ戻った翌年、亡くなっています。67歳、当時としては長生きでした。
この旅には、旅人の息子家持(当時13歳くらい)も同行していました(大伴郎女は家持の実母ではないと考えられています)。家持は、どんな男の子だったのかなあ、と想像、すっかり家持に会った気分です。
旅人や家持が太宰府に滞在している間に、都では、長屋王の変があり、藤原氏が政権の中枢を占めていました。旅人死後、大伴家の惣領として、家持は苦難の道を歩みます。
むろの木の横に可愛い薔薇が。福山市は薔薇の町として有名なんだそうです。「鞆の浦」と名付けられた薔薇。

この薔薇は多分「フクヤマ」だったと思うのですが、検索しても出てこない、、、、。綺麗でした。

福禅寺対潮楼。前述したいろは丸事件の交渉が行われた場所です。

座敷からは、仙酔島、弁天島がポッカリと浮かぶ、のどやかな景色が見えます。江戸時代朝鮮通信使はここを宿にしたそうで、この景色を日本で一番美しい景色と称えたそうです。朝鮮通信使は約1年近くかけて、海路、川路で京にいき、東海道を江戸まで行ったということで、地元では、富士にも琵琶湖にも勝る景色ということが、大いに自慢となっています。
いろは丸関連で使われた場所が、宮崎駿監督プロデュースにより、カフェ&宿に生まれ変わりました。空襲を受けることなく残された街並みも老朽化していたのですが、その街並みを残そうと努力が重ねられています。「崖の上のポニョ」の取材でここを訪れた宮崎監督は、この街が気に入り、ここ、「御舟宿いろは」の改築デザイン画を描きました。

窓のステンドグラスがお洒落です。時間があれば寄りたかった。

美しい街並みの先に、重要文化財「旧太田家住宅」がありました。1659年大阪の漢方医中村吉兵衛さんが、ここで保命酒を生み出しました。やがて保命酒は、備後の特産品として江戸幕府から庇護され、全国に知れ渡るようになりました。中村家から太田家に譲渡された家と保命酒レシピは、今に続いています。
https://visittomonoura.com/houmei-liquor/
酒蔵を見学後、ランドマークの常夜燈で、ガイドさんと別れます。とてもわかりやすい説明、ありがとうございました。



2時間の街歩きを楽しみました。ランチタイム後も、私たちのおしゃべりはとどまることなく続きました!
2024年6月22日 鞆の浦で、家持に会えたことも、とても嬉しかったです。